2024年春ドラマ『人事の人見』 ドラマなんかノーチェックだったけど、流石に労務の仕事やっててそりゃあかんやろとTVerで遅ればせながらチェックしてます。
その中で、第2話では、長時間働こうとする女性社員を人事部が止めるシーンが印象的でした。
この展開に対して、社会保険労務士として一つの大きな違和感がありました。それは、**労働基準法38条の3第1項に基づく「専門業務型裁量労働制」**の活用が全く検討されていなかったことです。
この記事では、裁量労働制の概要と、ドラマの描写における問題点、現場の人事担当者が押さえておくべき視点について詳しく解説します。
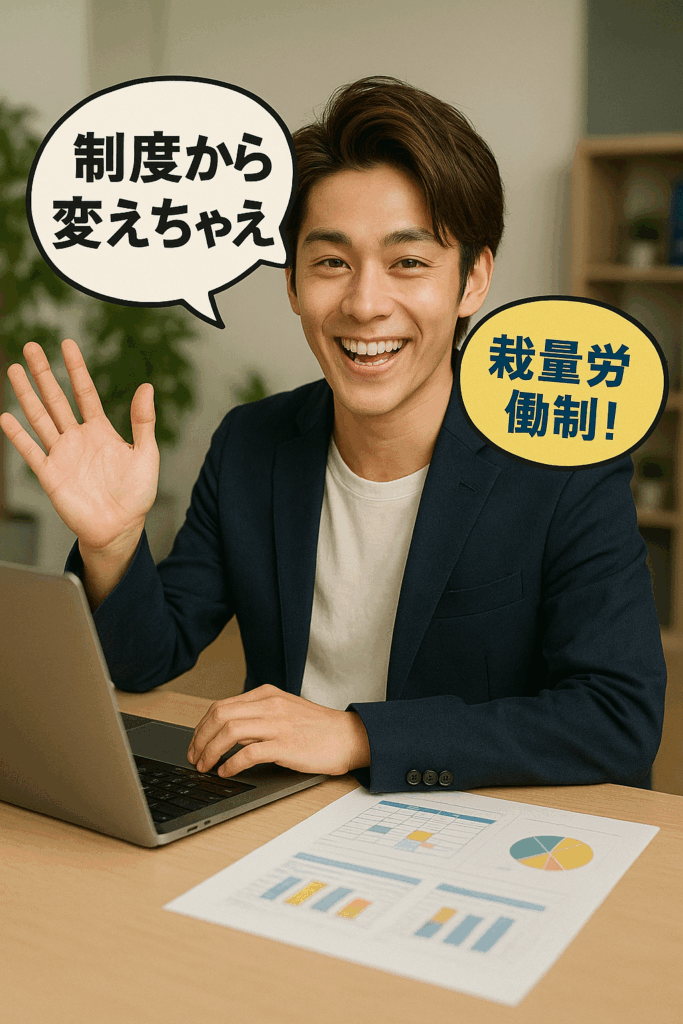
専門業務型裁量労働制とは、特定の専門職に従事する労働者に対して、実際の労働時間に関わらず、**あらかじめ定めた「みなし時間」**で労働したものとみなす制度です。
長時間労働が問題となる昨今、「働き方改革」における柔軟な労働時間管理の手段として注目されています。
劇中では、大企業の人事部が長時間働こうとする企画部門の女性社員に対して、制度ではなく「働きすぎるのはやめましょう」という説得で対応していました。
しかし、彼女の業務内容は明らかに「新商品もしくは新技術の研究開発」(労働基準法施行規則24条の2の2第2項1号)に該当しており、専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3第1項)の対象業務に該当するものです。
以下のような理由があるのかもしれません。
確かに、制度の運用を誤れば長時間労働の温床になるリスクもあります。
しかし、正しく導入し、適切な健康配慮措置や定期的な労働時間チェックがなされれば、自由度の高い働き方を実現する有効な制度です。
導入を検討する際には、以下のような観点が重要です:
人事制度は、社員の働き方と企業経営の両方を支える大切なインフラです。
制度に頼りすぎるのも危険ですが、制度を検討もせずに感情的対応に終始することもまた不適切です。
人事部門には、「人に寄り添う力」と同じくらい、「制度を知り、使いこなす力」が求められます。
ドラマのように労働基準監督署の指導を受けているような場面で、しかも大企業であれば、制度の活用可能性を一通り検討するのは基本中の基本です。
当事務所では、裁量労働制やフレックスタイム制など、労働時間制度の導入支援や運用改善のサポートを行っております。
現場に即した実務と制度の両立を支援いたします。
ご相談・お問い合わせは当事務所へお気軽にどうぞ。
『人事の人見』という作品を通じて、「人事の人を見る力」は確かに大切です。
しかし同時に、「制度を知る人事」でなければ、社員の成長も企業の成長も支えることはできない――そう感じさせられた一話でした。